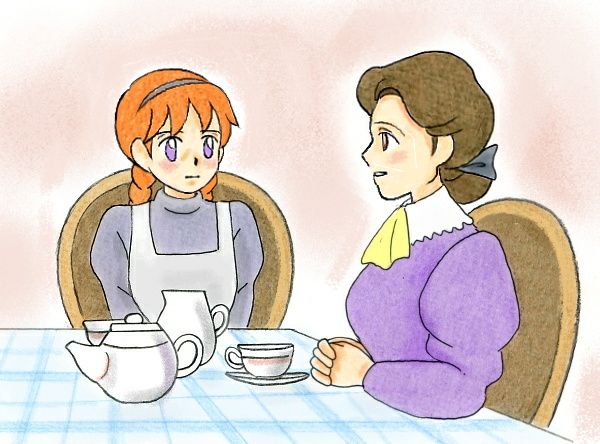 |
|||
| 「そうでしょうね。二人のことが気がかりだけど、 さりとてせっかく開けた未来への希望を捨てたくはないし、 いいえ、本当はもっと積極的にあなたの道を進んで行きたいんでしょう?」 「ええ、そうなんです。だから辛いんです。」 「じゃあ辛いまま、レドモンドカレッジへ行くしかないんじゃないかしら? いえね、アン。 人間は苦しいからといって、悩みを切り捨てるわけにはいかないのよ。 それが人間の良心というものなの。」 「あなたがそういう悩みを抱えているのを、私はとてもうれしく思いますよ。 良い成績で大学へ入れたからといって、 得意になっているだけでは、人間としてダメですものね。 人生というものは割り切れなくていいのよ、アン。 いいえ、割り切れてしまってはならないの。」 (赤毛のアン第46章「マシュウの愛」より) |
|||
「人生というものは割り切れなくていい、いいえ、割り切れてしまってはならない」 というアラン夫人の言葉、深みがあります。さすが牧師の奥さんですね。 辛い気持ちを抱えたままそれでも前に進んでいくことがある、人生ってそういうものなのよ、ということを アンに優しく諭します。 若いアンは純粋で真っ直ぐな考え方をします。 でも、人生を重ねたアラン夫人は、白か黒か、0か100かでは割り切れない、人の気持ちというものを 経験から分かっているのですね。 アンの人生に奥行きを与えてくれるアラン夫人は、アンにとってもう一人の恩師です。 |
|||
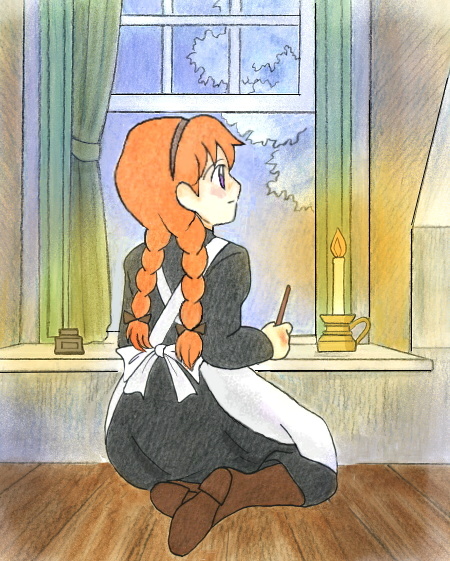 |
|||
| あたしの地平線はクイーン学院からこのグリーンゲイブルズに帰ってきた夜からみれば 極端に狭まってしまったのかもしれません。 しかし、たとえ私の足元にしかれた道がどんなに狭くとも その道にはきっと静かな幸せの花が咲いているに違いないと思います。 真剣な仕事と、立派な抱負と、好ましい友情を手に入れる喜びがあたしを待っています。 本当に道にはいつでも曲がり角があるものですね。 新たな角を曲がった時、その先に何を見いだすか、 私はそこに希望と夢を託してこの決断をしたつもりでした。 でも狭いように見えるこの道を、曲がりくねりながらゆっくりと歩み始めた時、 広い地平線に向かってひたすら走り続けていた頃に比べ、 まわりの美しいものや、人の情けに触れることが多くなったような気がするのです。 (赤毛のアン第50章「神は天にいまし、すべて世は事もなし」より) |
|||
「クィーンを卒業した時は、未来が一本のまっすぐな道のように思えたわ。 でも、今はそこに曲がり角があるのよ。角を曲がると、どんなことが待っているのか分からないわ。 でも、あたしは一番いいものがあるって信じてるの。だから全力を尽くしてやってみるわ。 そうすればきっとそれだけのものは返ってくると思うの。」 これもアンの言葉です。 それは、高速道路を走るか下の道を走るか、歩いていくか車に乗るか、という違いにも似ているかもしれません。 視野を広く持ち、道の端の草やすれ違う人々に目をやりながら、曲がりくねった道を歩んでいくことを選んだアンは とても生き生きとして魅力的に見えます。 壁にぶち当たったら、道なりに曲がってみるのもいいかもしれません。 |
|||
 |
|||
| 「もしあたしがマシュウの欲しがっていた男の子だったら、 今頃は大いに役立って、いろんな面で楽をさせてあげられたのにね・・・。 それを思うと、男の子だったら良かったのにって、 どうしても思っちゃうの。」 「そうさのう・・・。 わしはなあ、アン、 1ダースの男の子よりも、お前にいてもらうほうがいいよ。 いいかい、1ダースの男の子よりもだよ。 そうさのう。 エイブリー奨学金をとったのは男の子じゃなかったろう? 女の子さ。わしの女の子だよ。 わしの自慢の女の子じゃないか。」 「マシュウ・・・。」 「アンはわしの娘じゃ。」 (赤毛のアン第46章「マシュウの愛」より) |
|||
世界名作劇場では、親しい人との別れが描かれることがあります。 マシュウは若い人ではないし、原作は有名なので亡くなることは始めから分かっていました。 それでもこのシーンがこんなにも胸にくるのは、 この「赤毛のアン」というアニメが、丁寧に一話一話、描かれていたからだと思います。 一つ一つのエピソードからアンに対するマシュウとマリラの愛情が感じられ、 細やかに変わっていく絵からはアンの成長と、それと同時にマシュウとマリラの老いが伝わってきました。 だからこそ、ただ悲しいだけではなく、あたたかい悲しさというか、やさしく泣かされるような感じがしました。 こういう作品を見ると、やっぱり最終回とか感動シーンだけ集めても感動は伝わってこないし、 40話とか50話の積み重ねがあってこそなんだなあと、改めて思います。 背景や声優さんのすばらしさもあったと思います。セリフまわしやナレーションも文学っぽくて まるで本を読んでるみたいな感覚がありました。 アンが真剣に泣くほどなんか笑ってしまうというマリラが好きでした。 HOMEへ |